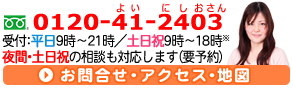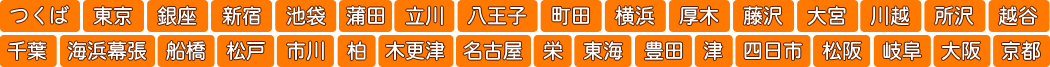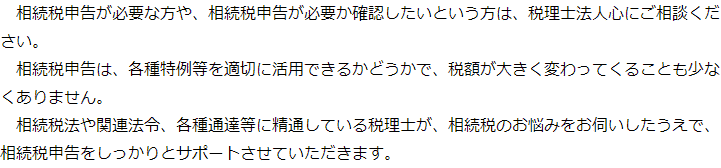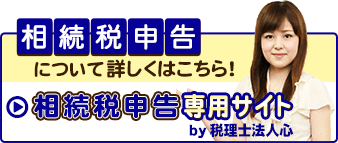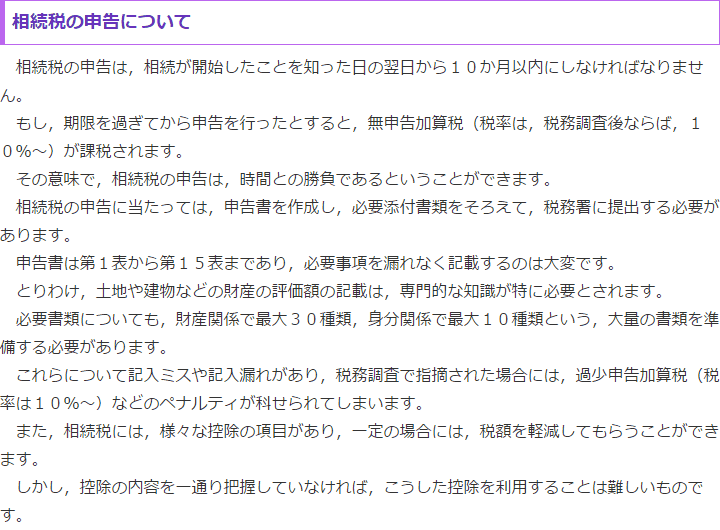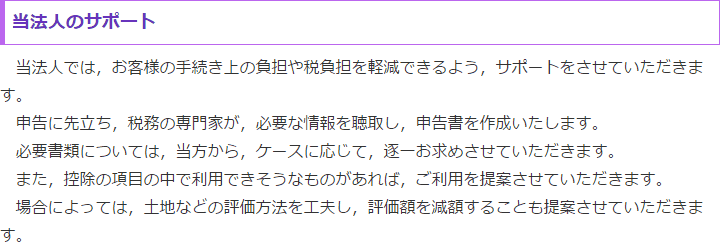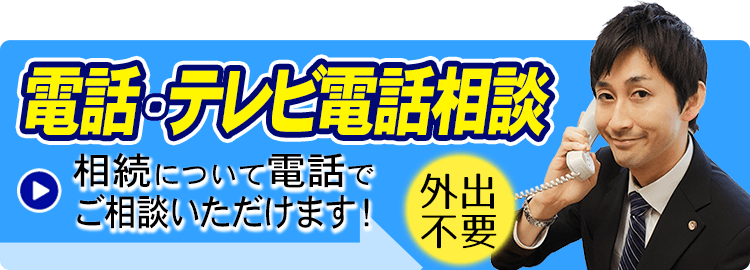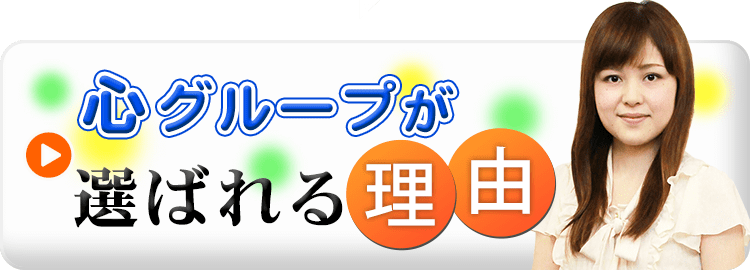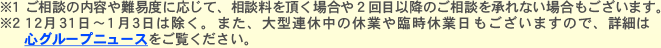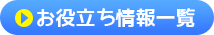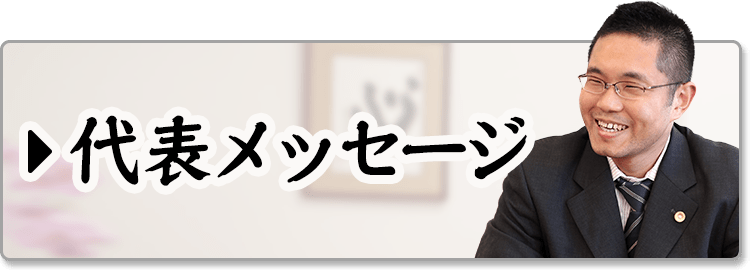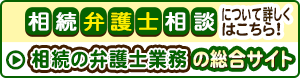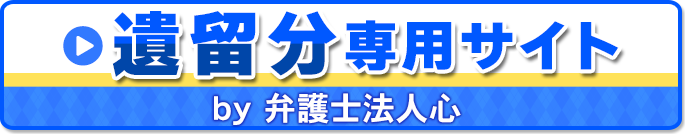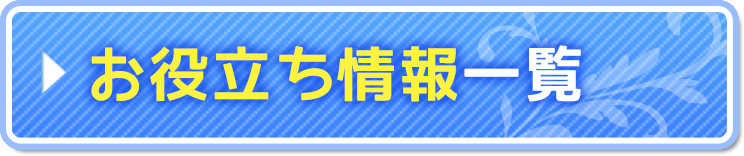相続税申告
千葉県内にも複数の事務所
私たちの事務所は複数ありますが、どれも駅から近い立地となっています。相談に足を運びやすい環境となっておりますので、お気軽にご利用ください。
相続税の申告が必要な場合
1 相続税申告はどのような場合に必要なのか

相続税の申告が必要なのは以下のような場合です。
①課税対象となる額が、相続税の基礎控除を超える場合
②申告しなくとも適用される控除を差し引いても、相続税額が上回る場合
相続人のほか、遺言によって指定された個人が、申告義務の対象となります。
2 相続税の基礎控除について
相続税が発生するかどうかについては、まず課税対象額と基礎控除を計算します。
⑴ 課税対象額
課税対象額は、プラスの財産からマイナス財産や葬儀費用を差し引いた額です。
プラスの財産とは、預貯金や現金、不動産、生前贈与(法改正で令和6年1月1日以降から3年の期間が段階的に7年に延長されました)などであり、マイナスの財産とは、ローンや未払いの入院費などをいいます。
たとえば、預貯金が2000万円、不動産が2000万円、ローンが500万円、葬儀費用が100万円だと、課税対象額は「2000万円+2000万円-500万円-100万円=3400万円」となります(説明の便宜上、いったん基礎控除を考慮していません。)。
⑵ 基礎控除
相続税の基礎控除とは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
たとえば、法定相続人が2人であれば、基礎控除は「3000万円+600万円×2人」で、4200万円となります。
そうすると、上記のとおり課税対象額が3400万円である場合、基礎控除の4200万円以下であるため、相続税の申告が不要ということになります。
3 申告しなくとも適用される控除について
申告しなくとも適用される控除としては、基礎控除のほか、障害者控除、未成年者控除、数次相続控除などがあります。
一般障害者の控除額は、「(85歳-相続発生時の年齢)×10万円」、特別障害者の控除額は、「(85歳-相続発生時の年齢)×20万円」で、それぞれ計算されます。
また、未成年者が相続人となる場合、「(18歳-相続発生時の年齢)×10万円」で計算されます。
数次相続控除とは、被相続人が、亡くなる前10年間に相続税を納めていた場合に、その相続人の税額が軽減される制度です。
このような控除が適用され、結果的に非課税であれば、相続税を申告する必要はありません。
4 特例の適用を受けるためには相続税申告が必要な場合があります
上記のように、相続税申告をしなくても適用される控除がある一方で、配偶者に対する税額軽減や、小規模宅地等の特例などは、適用を受けるための条件として、相続税申告書を期限内に提出することが挙げられます。
これらの特例を利用して相続税の納税額が0円になる場合であっても、相続税の申告を行わなければいけないことに、注意が必要です。
本来であれば相続税申告が必要だったのに、必要ないと思い込み、申告していなかったということのないように、税理士にご相談ください。
相続税申告の流れ
1 財産の調査と相続税が課される可能性がある人の確認

相続税のことを検討するにあたり、まず初めにやるべきことは、被相続人の相続財産と、相続税が課される可能性がある人の確認です。
⑴ 財産の調査
被相続人の相続財産を調査しないと、相続税の計算ができませんし、把握できていない相続財産があった場合には申告漏れを起こしてしまう可能性もあります。
被相続人の財産の典型的なものとしては、現金、預貯金、土地、建物、株式や投資信託、債務があります。
細かいものとしては、過誤納付の還付金や、未払いの固定資産税などがあります。
また、相続税の計算の場合、生命保険金などもみなし相続財産として、相続財産に含まれるので注意が必要です。
⑵ 相続税が課される可能性がある人の調査
まずは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を収集します。
これらの書類は、他の相続の手続きにおいても使用することが多いので、収集しておくと便利です。
相続人以外に、遺言によって財産を取得する人(受遺者)がいる場合は、受遺者についても調査します。
相続人以外に死亡保険金を受け取った人がいる場合は、その人も相続税が課される可能性があるので、漏れなく確認するようにしてください。
⑶ 相続税発生の有無
相続財産(みなし相続財産含む)が一定の評価額を超える場合、原則として相続人や受遺者の方は、取得した財産の評価額に応じ、相続税の申告および納付をする義務を負います。
相続財産全体の評価額と、相続人の人数の調査ができた段階で、相続財産全体の評価額が基礎控除額以下であるか否かの計算ができます。
この時点で基礎控除額以下であれば、相続税は課されないと判断することができます。
2 遺言の確認と遺産分割協議
遺言がある場合は、その内容を確認し、誰がどの相続財産を取得するかを確認します。
遺言が無い場合、または遺言に記載されていない相続財産がある場合、相続人間で遺産分割協議を行います。
その後、遺産分割協議書を作成し、相続人が実印を押印した上で印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の写しと相続人の印鑑証明書(原本)は、相続税申告の際にも使用します。
これにより、誰がどの財産を取得するかが決まりますので、各相続人、受遺者の相続税額の計算が可能になります。
また、相続財産の取得の仕方によっては、各種の特例が適用され、相続税を低減することができる場合もあります。
そのため、誰がどの財産を取得するのかを話し合う際は、相続税のことも考慮するとよいかと思います。
3 相続税額の計算
相続財産とみなし相続財産の評価額から、遺産総額を求めます。
預貯金や現金は金額がそのまま評価額となりますが、土地、建物、株式等はそれぞれ評価方法があります。
特に土地は、路線価方式または倍率方式という計算方法で評価します。
路線価方式の場合、形状によってはさらに評価額が下がることもあるので、複雑な評価が必要になることもあります。
参考リンク:国税庁・路線価方式による宅地の評価
遺産総額から、相続債務、葬儀費、死亡保険金非課税枠等を控除し、課税価格を求めます。
課税価格から相続税の総額を計算した後、各相続人、受遺者の相続税額を計算します。
配偶者、未成年者、障害者の方などの場合、さらに相続税の控除が適用されることもあります。
4 相続税申告、納付
⑴ 申告書の提出
相続税の計算が完了し、申告書が完成したら、税務署に申告書を提出します。
その際、相続人のマイナンバーを確認できる書類の写し、遺産分割協議書の写し、相続人の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続財産に関する資料の写し(預貯金通帳、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、株式の評価計算書等)を添付します。
⑵ 相続税の申告期限
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月です。
申告期限までに、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税申告書を提出することで、申告は完了します。
⑶ 相続税の納付
相続税申告に加え、納付も必要になります。
税務署で納付書を受取り、納税額等を記載したうえで、金融機関等で納付をします。
納付の期限も、申告と同じく被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月ですので注意が必要です。
相続税を適切に申告しなかった場合の不利益
1 ペナルティが課されるおそれがある

相続税を適切に申告しなかった場合、ペナルティとして、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税を追加で支払わなければならなくなります。
相続税を適切に申告しなかった場合というのは、大きく2つの類型に分けられ、それぞれ課せられるペナルティが異なります。
まず一つめは、相続税の申告期限(相続の開始を知った日から10か月)までに相続税の申告を行わなかったというものです。
二つめは、相続財産の調査漏れや、意図的な相続財産の隠匿などによって、本来申告しなければならない金額よりも少ない相続税額の申告を行ったというものです。
この両方に該当する場合には、どちらに対するペナルティも課せられることになります。
以下、詳しく説明します。
2 期限後の申告または修正申告をした場合には延滞税が課せられる
相続税の申告期限を過ぎてから相続税の申告を行った場合や、申告期限までに申告をしたものの、申告時点では把握できていなかった相続財産が発見されたため、後から修正申告書を提出したという場合には、申告期限から相続税の納付を行った日までの期間に応じて、延滞税を支払わなければならなくなります。
延滞税は、利息と同じような性質を持っていることから、早く納付するほど金額は小さくなります。
相続税の申告が遅れてしまったり、期限後に修正申告をしたとしても、できるだけ早く納付することで延滞税を最小限に抑えることができます。
延滞税の金額の計算はとても複雑です。
詳しい計算は、国税庁がホームページで公開していますので、ご参照ください。
参考リンク:国税庁・延滞税の計算方法
3 期限後の申告をした場合には無申告加算税が課せられる
期限までに相続税申告をしなかった場合には、原則として、無申告加算税が課されます。
被相続人が亡くなったことは、通常であれば自治体が把握しており、被相続人がある程度の財産を有していた場合には、税務署はそのことを把握しているケースがあります。
そして、相続税の申告期限後、税務署の調査が入る前に相続税の申告、納付をした場合には、5%の無申告加算税が課せられます。
また、相続税申告期限までに申告をしないまま税務署の調査が入ってしまい、そのあとになって相続税の申告をした場合には、税額が50万円以下の部分に対しては15%、税額が50万円超え~300万円以下の部分については20%の無申告加算税が課せられます。
300万円を超える部分については、30%の無申告加算税が課せられます。
ただし、相続税の申告期限から2週間以内に申告をした場合には、無申告加算税はかかりませんので、相続税の申告をしていなかったとしても、できる限り早く対応すべきといえます。
4 少ない税額を申告した場合には過少申告加算税が課される
相続税は自身で計算して納めなければいけません。
それゆえ、相続財産の把握漏れや評価のミスなどによって、相続税の申告書に記載された税額が本来納めるべき税額よりも少ない税額を申告してしまうというケースが起こり得るのです。
申告期限までに相続税の申告をし、申告書に記載されたとおりの相続税を納付したものの、上記のような理由から申告額が本来納める税額よりも少なかった場合には、過少申告加算税が課されます。
相続税の計算の誤りに気付き、自分から修正申告をしたうえで正しい税額を納付した場合には、過少申告加算税は課せられません。
しかし、申告した税額が本来納めるべき税額よりも少ないことを税務署から指摘されたあとになって修正申告をした場合、納税額に対して10%の過少申告加算税が課せられてしまいます。
さらに、申告したときの税額と50万円とをくらべて大きい金額を超える部分については、15%の加算税が課せられます。
5 悪質性が高いとされる場合には重加算税が課せられる
相続税の支払い額を減らすために故意に少ない相続税の申告をしたり、申告自体を行わなかった場合には、いわゆる脱税となり、悪質性が高いと考えられることから、重加算税というペナルティが課せられます。
具体的には、次のとおりです。
まず、相続税の評価額を意図的に低くするため、相続財産の隠匿(いわゆる財産隠し)や、相続財産の存在を裏付ける書類の偽装した場合には、追加で支払う相続税の35%が重加算税として課されます。
次に、相続税が課せられないように相続財産を隠匿したり、相続財産を裏付ける書類を偽装し、相続税の申告自体をしなかった場合には、相続税総額の40%もの重加算税が課されます。
相続税の特例にはどのようなものがあるか
1 実務上重要な相続税に関係する特例について

お亡くなりになられた方が一定の評価額を超える相続財産をお持ちであった場合、相続人等には相続税が課せられます。
もっとも、政策的な理由等により、一定の要件を満たす場合には、相続税や所得税を軽減する特例がいくつか設けられています。
実務上重要なものとしては、小規模宅地等の特例、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例、農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例が挙げられます。
以下、それぞれについて説明します。
2 小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす場合に、被相続人のご自宅の宅地や事業用の土地の評価額を大幅に下げることで、相続税を低減することができる特例です。
土地は基本的に高額であるため、評価額が大きく下がると、相続税も大きく低減されます。
実務上も、多くの相続税申告において利用されています。
小規模宅地等の特例が適用される土地は3種類あります。
まず一つめは、特定居住用宅地等です。
特定居住用宅地等とは、被相続人、または被相続人と生計を一にする親族が住んでいた土地のことをいいます。
実務上多く見られるものとしては、被相続人のご自宅の宅地が該当します。
特定居住用宅地等の面積のうち、330㎡までの部分について、相続税評価額が80%減額されます。
二つめは、特定事業用宅地等です。
特定事業用宅地等とは、被相続人、または被相続人と生計を一にする親族が事業を行うために使用していた土地のことをいいます。
特定事業用宅地等のうち、400㎡までの部分について、相続税評価額が80%減額されます。
三つめは、貸付事業用宅地等です。
貸付事業用宅地等とは、被相続人、または被相続人と生計を一にする親族が貸している土地のことをいいます。
貸付事業用宅地等のうち、200㎡までの部分について、相続税評価額が50%減額されます。
3 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
正確には相続税を低減するものではありませんが、相続税がかかった相続財産を売却した場合に、譲渡所得税を低減できる特例です。
特に、不動産を相続によって取得しても、その不動産を使う予定がないため売却するということもあるかと思います。
このような場合に、譲渡所得税を低減できるのは、相続人としても助かります。
財産を売却した場合、基本的には、売れた金額から取得にかかった金額を差し引いて利益が生じている場合には、利益に対して譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得税の計算上、取得費が大きくなると利益が減り、譲渡所得税は低減されます(売却金額よりも取得費の方が大きい場合には、譲渡所得税はかからなくなります)。
そして、相続によって財産を取得した際に、相続税を支払っている場合には、当該財産を売却する際の取得費に、相続税額のうちの一定金額を加えることができます。
これによって、相続財産を売却した際の譲渡所得税を抑えることができます。
参考リンク:国税庁・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
4 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
被相続人が都市部にお住まいであった場合などにはあまり農地を持っているということはありませんが、地方にお住まいであった場合には農業を営み、農地を所有していることもあります。
そして、農地に相続税を課すと、相続税納税等のために農地を売却せざるを得なくなる可能性があります。
このようなことが繰り返されると農業の衰退につながることから、一定の要件を満たす形で農地を相続した場合には、相続税の支払いの猶予を受けることができるようになっています。
農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例の適用を受ける要件は複雑ですが、基本的には農家を継ぐ方が農地を相続し、かつ農業を続ける場合に適用を受けることができます。
そして、農地を相続した人が農業を続け、亡くなった場合には当該農地に関する相続税の納税が免除されます。