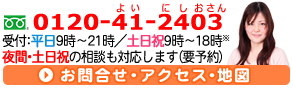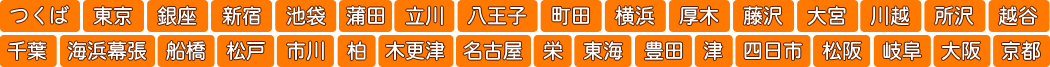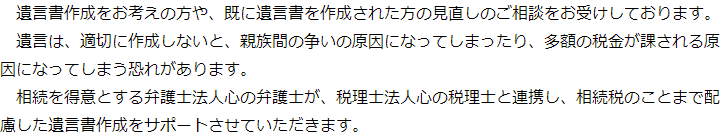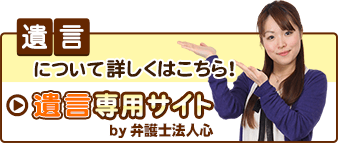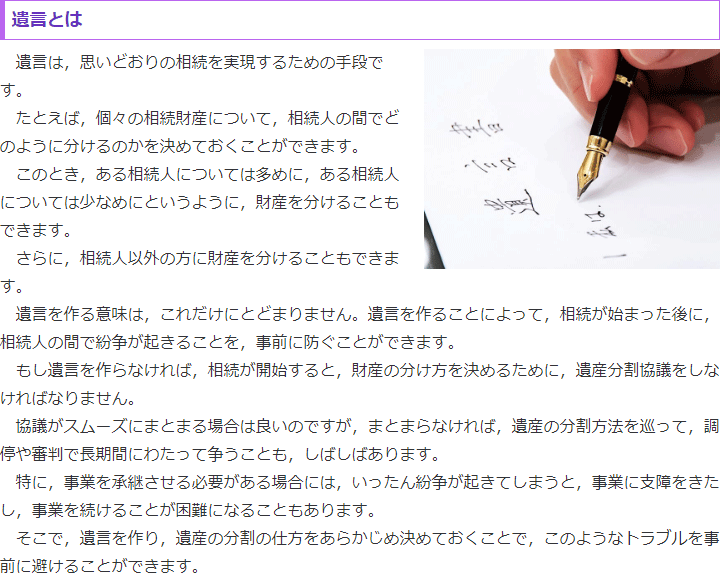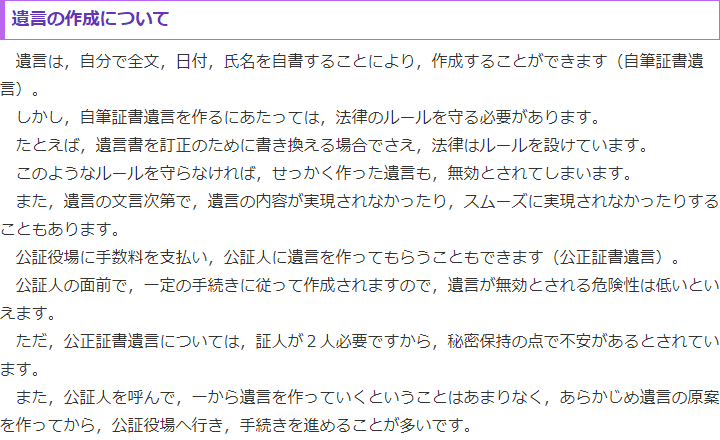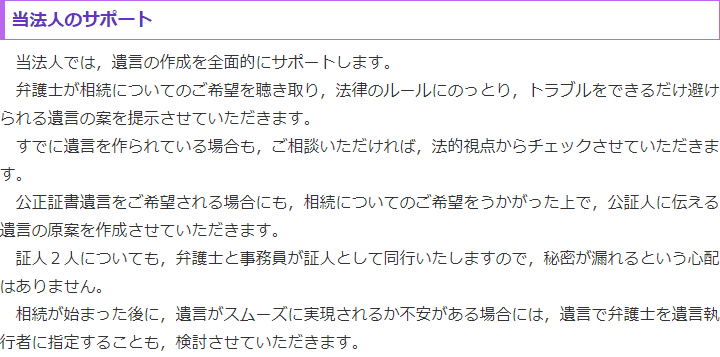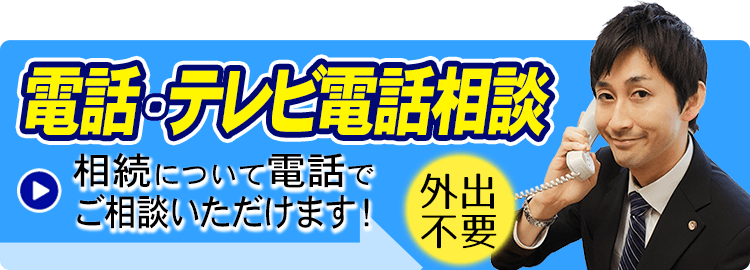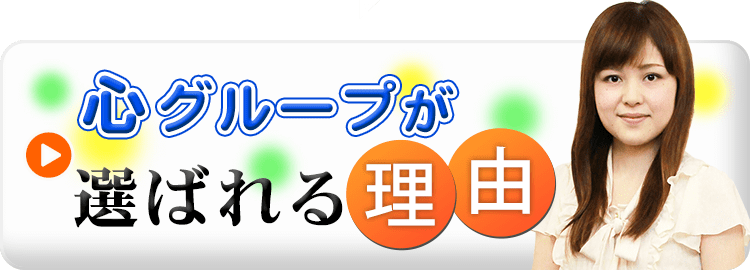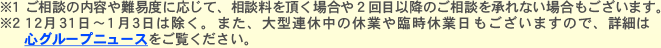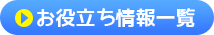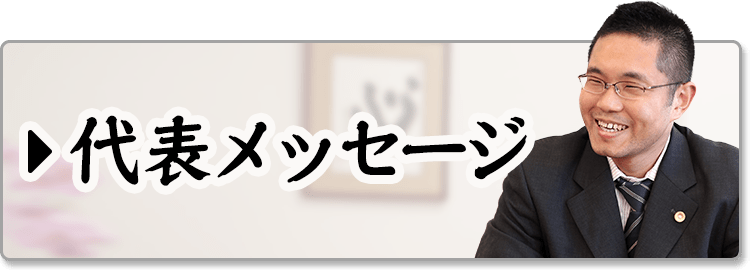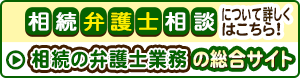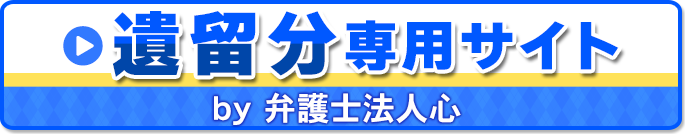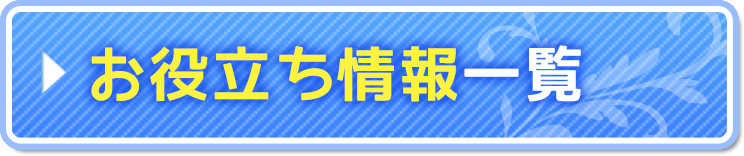遺言
遺言を作っておくべき人
1 誰にどの財産を取得させるかを決めている場合

特定の財産を特定の相続人に取得させたいような場合、その旨の遺言を作成しておくことによって、被相続人の意思を反映させた相続を実現させることができます。
ただし、遺留分などを考慮した遺言を作成することが大切です。
遺言を作成していないと、相続発生後に、相続人同士で遺産の分割方法を決めることになるため、被相続人の意思を反映させることができません。
2 相続人以外の者に財産を取得させたい場合
たとえば、子の配偶者・孫、お世話になった知人、内縁の妻・夫などに財産を取得させた場合や、慈善団体に寄付したい場合などは、遺言に記載しておけば、財産を残すことができます。
3 相続人同士での話し合いが困難であることが予想される場合
前妻の子と後妻など、相続人同士での話し合いが困難であると予想される場合は、遺言を作成することで、相続発生後に遺産分割協議を行う必要がなくなります。
相続人全員で話し合わずに済むため、相続人の負担を回避することができます。
4 子がいない夫婦
子がいない夫婦の場合、相続人が配偶者と亡くなられた方の尊属(父母、祖父母)になります。
亡くなられた方の尊属(父母、祖父母)も死亡している場合は、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。
しかし、亡くなられた方の配偶者と兄弟姉妹とが、遺産分割協議を協力的に行えるとは限らず、心情的にも難しいケースが多いです。
したがって、配偶者の生活を守るために、すべての財産を配偶者に残したいと考えるような場合には、遺言を作成しておくとよいです。
5 子・配偶者がいない人
子・配偶者がいない人で、たとえば兄弟姉妹の一部にだけ財産を残したいと考えるような場合も、遺言を作成することが有効です。
6 相続人が誰もいない人
相続人が誰もいない場合であっても、お世話になった人に財産を残したい等の希望がある場合には、遺言を作っておくとよいです。
遺言を作成しなくとも、その人自身が、特別縁故者として家庭裁判所に申し立てを行えば、認められる可能性はあるものの、時間や費用、労力がかかってしまいます。
また、特別縁故者に該当しない場合や、特別縁故者に該当するが一部のみ財産を取得するにとどまる場合には、共有不動産は他の共有者のものとなります。
そういった事情もない場合には、亡くなった人の財産は、最終的には国のものとなります。
遺言を作成するタイミング
1 遺言の作成が可能なタイミング
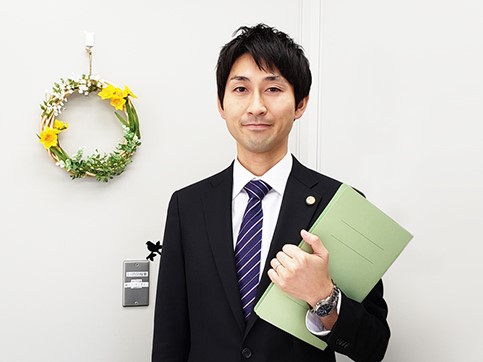
民法上、15歳以上であれば、何歳でも遺言を作成することができます。
60代以降で作成する方が多いようですが、決まりがあるわけではありません。
財産や人的関係について把握・整理し、必要に応じて、できればお元気なうちに作成をするのがよいでしょう。
作成する年齢に上限はないのですが、遺言をするときにその内容を理解し、どのような結果が生じるのかが分かる能力がなければ、その遺言は無効となってしまいます。
そのため、認知症などによって判断能力が低下する前に、遺言書を作成する必要があります。
2 遺言の作成を検討するタイミング
遺言書がなくとも、法定相続人が協議や調停・審判によって遺産分割をすることはできますが、遺言書があればよかったという場合も少なくありません。
遺言書を作成することによって、ご自身の希望を実現したり、残された者の生活を守ったりすることができます。
遺言の作成を検討するタイミングとしてよくあるケースをご説明いたします。
⑴ 特定の相続人に特定の財産を取得させたい場合
ある相続人に対し、特定の財産を取得させたいなどの希望がある場合、遺言書を作成すればそれが優先されますが、それがなければ遺産分割協議や調停・審判の結果、誰が取得するかが決まることになります。
また、相続人以外の者に対し、自己の財産を取得させたいような場合には、遺言書を作成しておく必要があります。
たとえば、法定相続人とは何十年も疎遠であるが、お世話になった身近な知人に財産を取得させたいとお考えの場合などです。
⑵ 相続における家族の負担を減らしたい場合
遺言書を作成しておけば、遺産分割に関する家族の負担を減らすことができるというのも、大きなメリットといえます。
遺産分割であれば、戸籍謄本等の必要書類を収集して他の相続人に連絡をとらなくてはならず、労力や時間がかかります。
また、遺言書の作成によって紛争を予防できる可能性も高まります。
⑶ 財産や親族の関係が変わる場合
たとえば、結婚・離婚、出産、就職・退職、病気・近親者の死亡などによって、財産や人的関係が変わる場合、それによって財産を引き継がせたい相手や内容が変わるかと思いますので、そういったタイミングに遺言の作成を検討するのもよいです。
3 遺言を書き直すタイミング
遺言書は、遺言者が最後の意思表示を行うものではありますが、一生に一度しか作成できないというものではありません。
何回でも、遺言の方式に従って、全部又は一部を撤回し、書き直すことができます。
たとえば、Aさんに不動産を遺贈するものとして遺言書を作成したが、先にAさんが亡くなってしまったので、新たにBさんに遺贈する遺言書を作成するような場合です。
このように、状況が変われば遺言書を書き直すことはできるので、早めに検討し、備えておいたうえで、必要に応じて見直すということも可能です。
遺言書を作成する場合の注意点
1 すべての財産についての遺言を作成する

財産のうち、一部についてのみ遺言を作成することは、基本的には問題があります。
例えば、千葉に不動産AとBを所有しており、その他に預貯金6000万円の財産がある場合に、「不動産A(価値3000万円)をXさんに、不動産B(価値5000万円)をYさんに相続させる」のように、不動産のことを記載しただけでは、遺された預貯金6000万円をどのように分けるかで揉める可能性があるからです。
上記のようなケースの場合、判例では、全体の法定相続分を変えない趣旨である前提で、預貯金はXさんが多く受け取るというのが遺言者の意思であると解釈することが多いです。
しかし、他の証拠から、それとは反対の事実が出てきた場合などには熾烈な争いとなってしまうこともあります。
このように、相続トラブルに発展してしまうおそれがありますので、遺言を作成する際には、すべての財産について記載するようにしてください。
また、遺言作成時点には存在しない財産に備えて「上記以外の遺産についてはⅩに相続させる」等、包括的な記載にしておくのも一つの方法です。
2 遺産に大きな変動が生じる可能性も考えて作成する
たまにあるトラブルとしては、「Ⅹさんに不動産A(価値5000万円)、Yさんに不動産B(価値5000万円)、預貯金1億円はⅩさんとYさんに半分ずつ」という内容の遺言を遺したものの、後日不動産Aを売却したというケースです。
売却後に相続が発生してしまうと、Aの部分だけが無効になりますので、Yさんは不動産Bを取得したうえで、預貯金は半分ずつ分けることになってしまい、Ⅹさんにとっても遺言者にとっても想定していない事態となってしまうケースがあります。
遺産に変動が生じた場合には、遺言の作り直しが必要です。
3 予備的な遺言書
予備的な遺言書を作成することも検討すべきです。
例えば、「甥にすべての財産を譲る」という遺言を遺しておいたものの、自分より先に甥が亡くなってしまっていれば、遺言はその部分について無効になってしまいます。
遺言を書き直せばよいのですが、甥が亡くなった時点で、既に遺言者が認知症になってしまっていたら、遺言を作り直すこともできません。
このような事態に備えて、予備的な遺言書を検討すべきといえます。
記載内容としては、例えば、「すべての財産を甥に相続させる」という条項の後に、「甥が遺言者より先にまたは同時に亡くなっていた場合には、すべての財産を甥の嫁に相続させる」等のように記載します。
自分で遺言を作成する場合のメリットとデメリット
1 自分で遺言を作成する方法

遺言については、自筆証書遺言や公正証書遺言など、いくつかの作成方法が定められています。
このうち、自筆証書遺言については、ご自身が日付、氏名を自書し、原則として内容部分の全文を自書すれば作成することができます。
このため、自筆証書遺言は、いつでも、どこでも、ご自身で作成することができます。
専門家から一切の助言や関与を受けることなく作成することも可能です。
このように、専門家の助言や関与なく、自分で遺言を作成することについては、一定のメリットとデメリットがあります。
ここでは、自分で遺言を作成した場合のメリットとデメリットを説明したいと思います。
2 遺言の作成費用がかからない
まず、自分で遺言を作成した場合のメリットとして、一切の費用をかけずに作成することができる点が挙げられます。
たとえば、公正証書遺言を作成すると、公証人に公正証書という正式な文書を作成してもらう必要がありますので、公証人に手数料を支払う必要があります。
また、自筆証書遺言であっても、専門家の助言を受けたり、専門家に案文を作成してもらったりする場合には、専門家に相談料や報酬を支払う必要があります。
これに対して、専門家の助言や関与なく自筆証書遺言を作成すれば、ご自身で、一切の費用をかけずに作成することができます。
3 いつでも作成、変更することができる
自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば作成することができます。
専門家の助言や関与を求めないのであれば、専門家に問い合わせをしたり、日程調整をしたりする必要もありませんので、いつでも作成することができます。
また、遺言を変更したい場合も、いつでも変更分の遺言を作成することができます。
遺言を作成しようと思った際に、気軽に作成できるという点も、自分で遺言を作成するメリットであるといえます。
4 形式的な誤りが生じるおそれがある
遺言については、法律は、形式面でのルールをいくつか設けています。
遺言に形式面での誤りが生じると、大変な事態が生じます。
法律は、このような形式面でのルールを守っていない遺言については、無効と扱うものとしています。
加えて、遺言は、被相続人が亡くなった後に力を発揮するため、万一、この段階で遺言が無効であることが発覚した場合には、遺言を作り直すことは不可能になります。
遺言が無効になってしまうと、ほとんどの場合、法定相続分での遺産分割を余儀なくされることとなります。
このように、遺言に形式面での不備があった場合には、文字通り、取り返しのつかない事態が生じてしまいます。
自分で遺言を作成すると、こうした形式面でのルールを満たしていないものになるおそれがあり、遺言が無効になるおそれもあります。
こうした事態を防ぐためには、専門家によるチェックがあった方が望ましいと言えます。
5 内容面で不利益が生じるおそれがある
遺言の書き方によっては、法律的に有利になったり、税負担の観点から有利になったりすることがあります。
自分で遺言を作成すると、知らず知らずのうちに、内容面で不利な遺言になってしまうことがあります。
たとえば、同じ不動産でも、年間一定時間以上の農業従事者であれば、土地上に建物を建てることができ、宅地利用することができる場合があります。
一方そうでなければ宅地利用ができず、土地をまったく活用できないといった事態が起きることがあります。
こうした事態を避けるためにも、公法規制、税制に詳しい専門家の助言を得ることをおすすめします。
遺言執行者の選び方
1 遺言執行者の資格要件

民法上では、未成年者と破産者も遺言執行者になることはできないとされています(民法1009条)。
遺言執行者は、遺言者の財産を管理する権利・義務を有しますので、遺言執行者となる人には、完全な行為能力が求められていますが、それ以外には特に明文上の制限はありません。
完全な行為能力は、単独で確定的に有効な法律行為をする能力をいいます。
遺言執行者には、法人もなることができますし、相続人や受遺者がなることもできます。
2 遺言による指定
遺言者が遺言執行者を指定する場合には、必ず遺言によらなければなりません。
遺言で遺言執行者を定める場合、遺言者が直接遺言執行者を指定することは勿論、遺言執行者の指定を第三者に委託するという定め方もできます(民法1006条1項・2項)。
3 家庭裁判所による選任
遺言書に遺言執行者が指定されていない場合や、指定されていた遺言執行者が死亡した場合等には、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることにより、遺言執行者を選任することができます。
申立てできる人は、利害関係人です。
遺言執行者の選任の申立があった場合、家庭裁判所は、候補者について、欠格事由の有無、適格性、就職の意向などを審理することとなります。
家庭裁判所が選任の審判をするには、候補者の意見を聴かなければならないとされており、実務上は家庭裁判所から照会書が遺言執行者の候補者と申立人に対して送られる運用が採られています。
家庭裁判所による候補者の適否についての検討が完了すると、遺言執行者選任審判がなされます。
遺言執行者選任の申立てを認容する審判の場合には、申立人および遺言執行者に対して審判書の謄本が送付されます。
一方で、申立てを却下する審判の場合には、申立人に対する送達の方法により告知されることになります。
この申立てを却下した審判に対しては、申立人その他の利害関係人から即時抗告の申立てをすることができます。