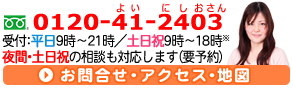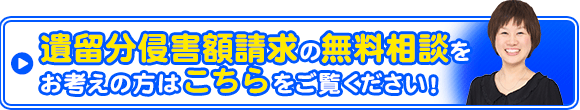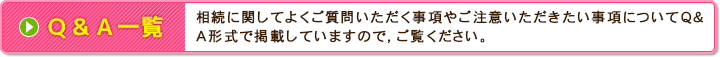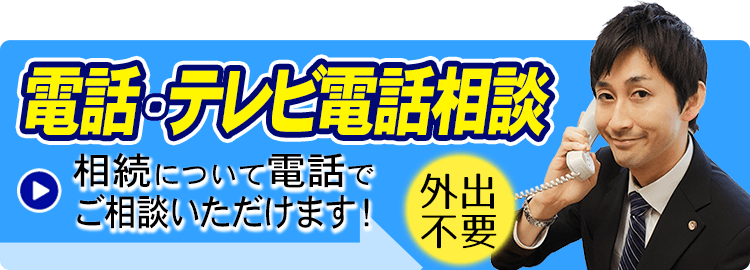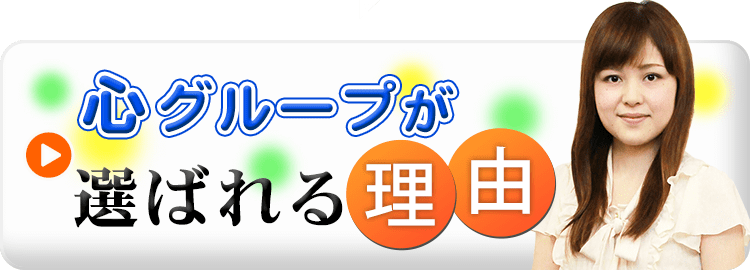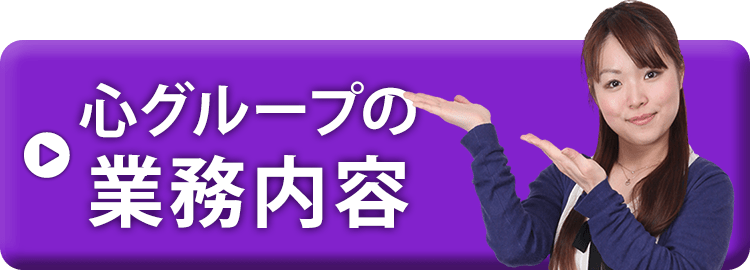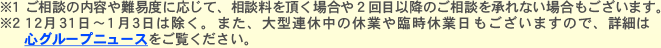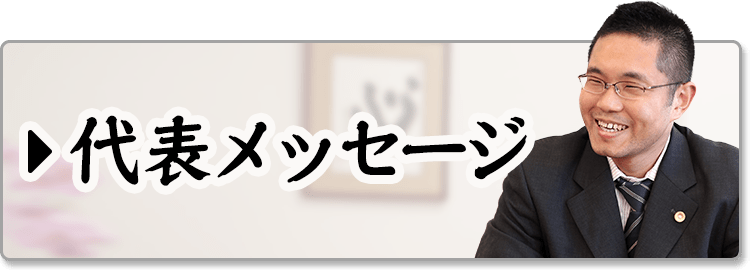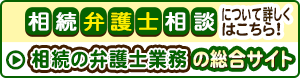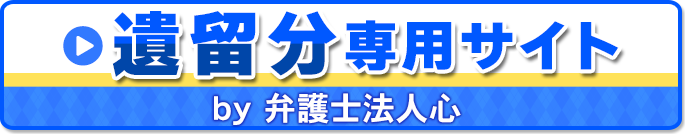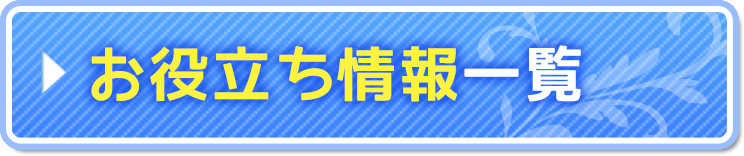遺留分の期限
1 遺留分侵害額請求には1年の期間制限があります
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の遺産取得分です。
しかしこの権利は、いつまでも保障されているかというとそうではなく、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に請求をしないと、時効によって消滅してしまいます。
1年もあれば十分ではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続後は様々な手続きがありますし、仕事が忙しいなどで権利を行使しないまま放置していると、1年という期間はあっという間に経過してしまいます。
そこで、遺留分侵害額(民法改正前は遺留分減殺)の請求は、できるだけ速やかに行う必要があります。
2 いつから1年の期間制限がスタートするのか
1年の期間制限は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時からスタートします。
例えば、被相続人が死亡してから1年後に遺言書が発見され、特定の相続人に全財産を相続させると記載されていた場合、その記載内容を知った時から1年の期間制限がスタートします。
反対に、被相続人が特定の相続人に全財産を相続させるという内容の遺言書を作成したことは被相続人の死亡前から知っていたものの、被相続人の死亡時に海外の紛争地域で取材をしていた等で国内の親族と連絡が取れず、被相続人が死亡してから1年後に死亡の連絡を受けた場合、1年の期間制限はその連絡を受け被相続人の死亡を知った時から開始します。
3 10年の期間制限という制度もあります
遺留分侵害額の請求権は、相続が開始した時から10年を経過したときにも消滅します。
例えば、亡くなった方と疎遠だった場合や、ずっと海外で生活しているような場合は、ご家族が亡くなったことを知らないまま過ごすということもあり得ます。
また、ご家族が亡くなったことを知っていても、特に遺産のことが話題に上がらず、相続のことがずっと放置されているようなこともあり得ます。
このようなケースのように、相続の開始や遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知らなかった場合であっても、相続開始から10年が経過してしまうと、遺留分の請求はできなくなります。
4 相続発生後は早い段階で専門家にご相談ください
遺留分侵害額の請求権には、厳しい期間制限があるため、この期限内に請求を行う必要があります。
請求の仕方に決まりはありませんが、遺留分の請求をしたことの証拠を残しておかなければ、後で裁判になった際に、期間制限を遵守したことを証明することが困難となってしまい、不利な結果になる可能性があります。
適切な方法で遺留分の請求を行うため、相続発生後すぐに遺留分など相続に詳しい専門家に相談し、解決のためのアドバイスを受けることをおすすめします。
遺留分の請求をお考えの方はもちろん、自分の遺留分が侵害されているかもしれないと感じた場合には、できるだけお早めに専門家へご相談ください。
自分の場合は遺留分の請求ができるのか、できるとしたらいくらくらいの額を請求できるのか等のご相談もお受けしています。
私たちは、遺留分をはじめとする相続の問題に幅広く対応できます。
相続に関するご相談は、原則として無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
遺産分割に納得できない場合の対応 遺留分を請求する際によく争われるポイント