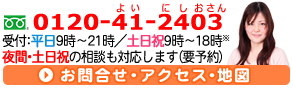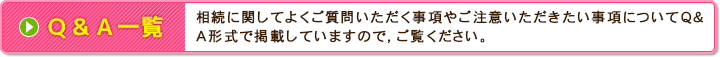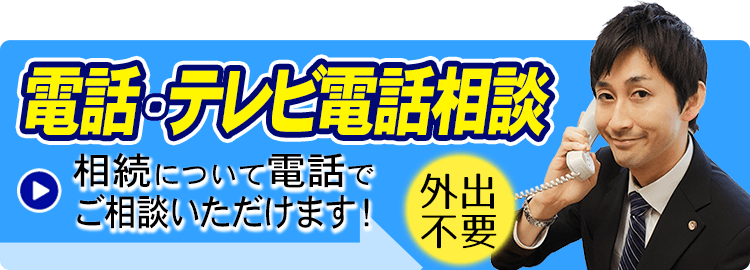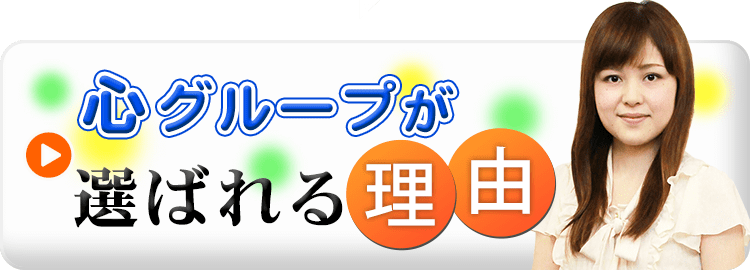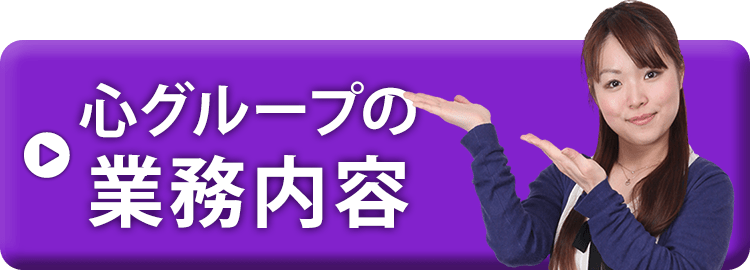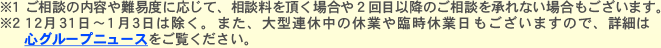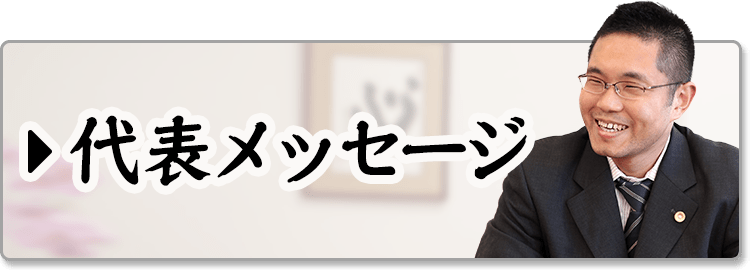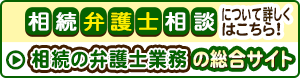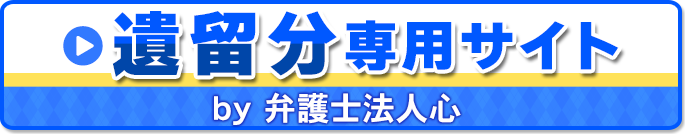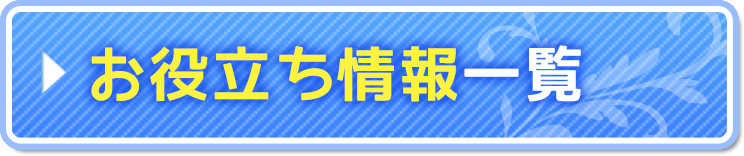相続で預貯金を解約する方法
1 まずはどの銀行に口座があるのかを調べましょう
相続が発生した後は、亡くなった方の預貯金を解約し、預貯金を相続する必要があります。
そのため、まずは財産調査を行って、どの銀行に口座があるのか、預貯金がいくらあるのか等を確認します。
口座番号が分からない場合など、財産調査の方法についてはこちらでも説明していますので、ご覧ください。
もし、多額の預貯金があるのに、その存在を見逃してしまった場合、非常にもったいない結果にもなりますし、遺産分割が終わった後にその預貯金が見つかると、その預貯金についてどのように分けるのかを再び話し合わなければならなくなりますので、財産調査は慎重に行う必要があります。
財産調査は専門家に依頼することもできますので、ご不安な場合は一度ご相談ください。
2 戸籍謄本を集めましょう
どの銀行に預貯金があるのかが判明したら、次は自身が相続人であることの証明が必要です。
銀行側からすれば、口座を持っている人が亡くなったのかどうか、解約のために窓口に来た人が相続人なのかどうかは、判別することができません。
そこで、戸籍謄本を集めて、ご家族が亡くなったことや、自分が相続人であることの証明を行う必要があります。
相続人が、亡くなった方の子や配偶者である場合は、集める戸籍が少なくて済みますが、相続人が亡くなった方の親であったり、兄弟姉妹であったりする場合には、非常に多くの戸籍が必要になります。
場合によっては、かなり古い戸籍を取得する必要がありますが、古い戸籍は全て手書きで作成されているなどして、とても読みづらいものが多く、戸籍の収集は容易ではありませんので、専門家に任せてしまうというのもひとつの手段かと思います。
3 相続人が複数いる場合は、預貯金の分け方を話し合いましょう
遺言書がなく、相続人が複数いる場合、遺産の分け方を決める必要があります。
誰が預貯金を相続するのか、どんな割合で相続するのかが決まっていないと、銀行側は誰にどれだけ預貯金を渡せばいいのか判断できないからです。
話し合いがまとまった場合は、相続人の間で遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書は、金融機関での手続きの際に必要となります。
4 銀行に提出する必要書類を集めましょう
預貯金の解約を行う場合、戸籍謄本の他に、各相続人の印鑑登録証明書も必要になります。
また、各銀行が用意している相続手続きの書類にも、記入が必要です。
金融機関によって必要な書類が異なる場合もありますので、詳細は各金融機関にご確認ください。
5 遺言書がある場合は、遺言執行者が預貯金の解約手続きを行います
もし遺言書があり、預貯金の相続方法が決められている場合は、遺言執行者が代表して預貯金の解約手続きを行うことになります。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の指定を申し立てます。
遺言執行者が預貯金の解約手続きを行う場合は、相続人同士での話し合いをする必要がないため、スムーズに解約手続きを行うことができます。